国内外でのつながりを
第二内科に還元したい
2007年入局
不整脈先端治療学 助教
林 克英
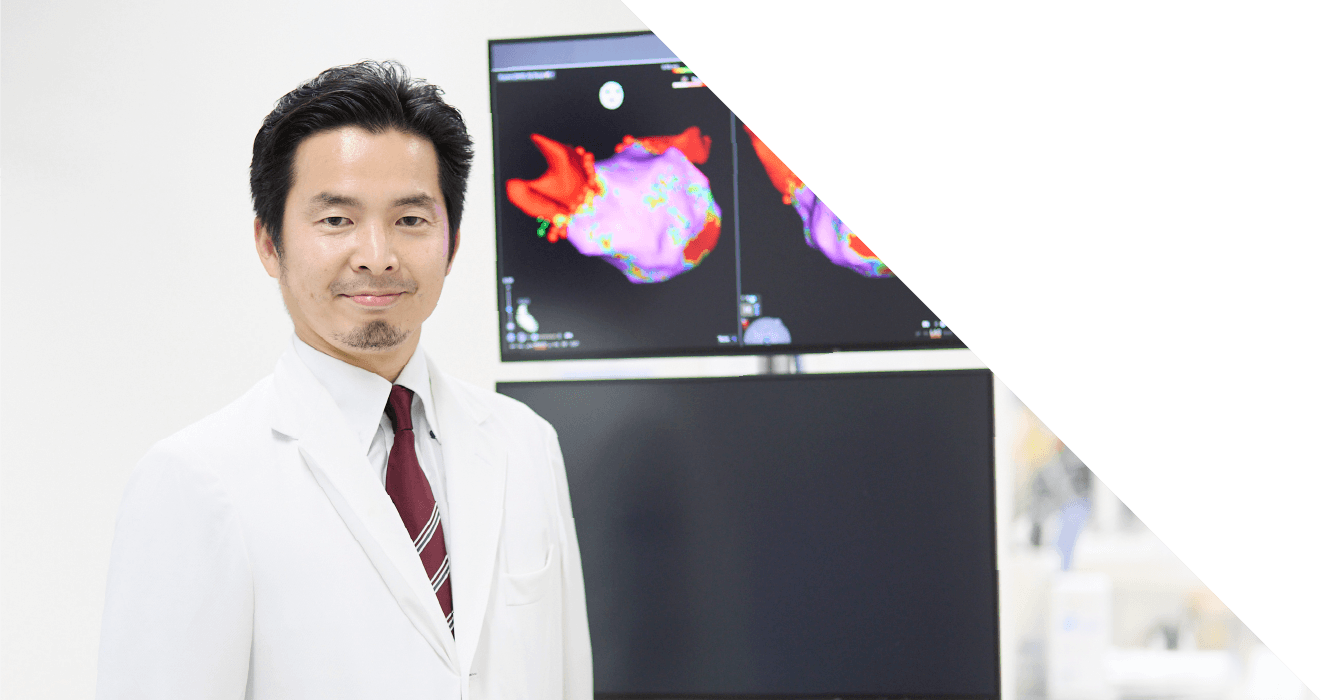
2007年入局
不整脈先端治療学 助教
林 克英
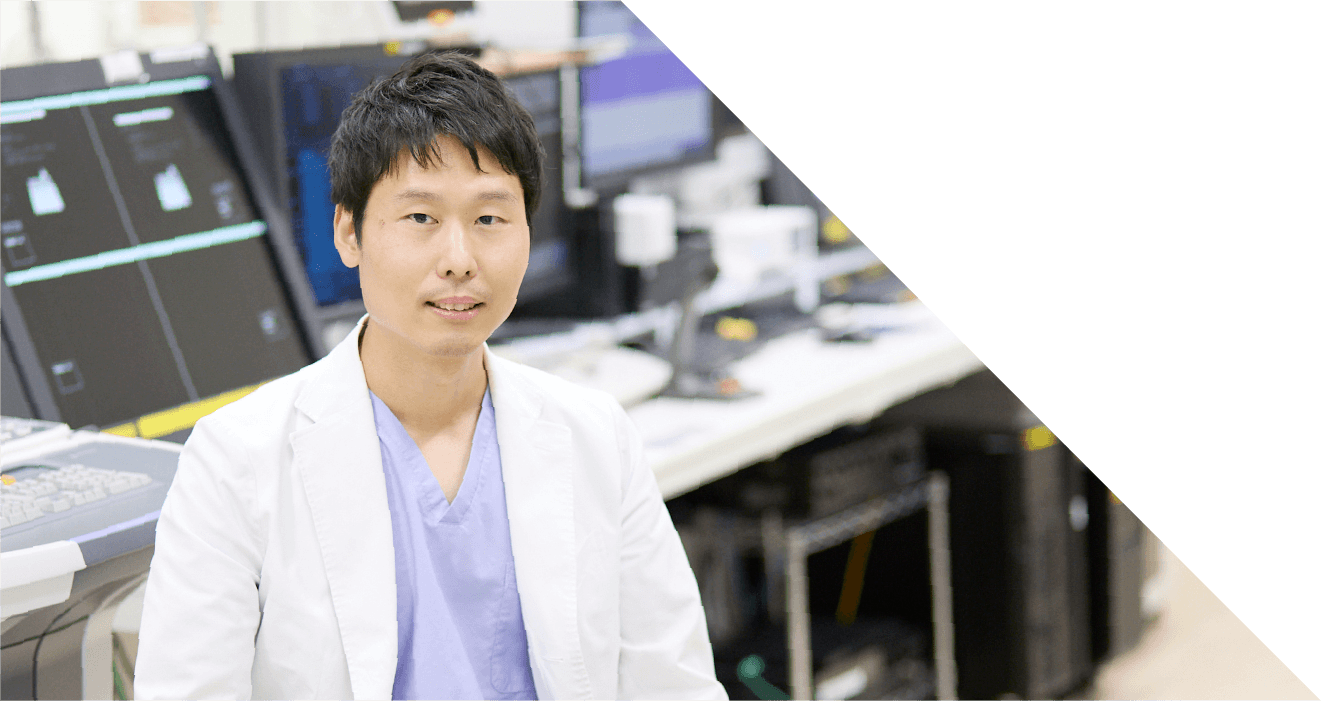
2013年入局
学内講師
岡部 宏樹
元々急性期の全身管理ができる科に興味を抱いていましたが、心筋梗塞で命の危険性がある患者さんをカテーテル治療にて救うことができる現場を学生の頃に目の当たりにし、循環器内科を志すようになりました。医師になった今、自分がそのような立場になり、学生の頃に思い描いていた想像以上の大変さ責任の重さを感じますが、それ以上に急性期をなんとか乗り越え、患者さんが無事に退院していくのを見るとそれ以上の充実感を感じています。
私は、カテーテル治療を通した医療を主なフィールドにしています。単にカテーテルと言っても、心臓血管だけではなく、足の痛みの原因となる末梢動脈疾患、突然死のリスクとなる大動脈瘤など全身の動脈硬化を原因としている疾患の治療を行っています。それぞれの血管部位に応じて求められる薬物治療、カテーテルの種類が異なりますので、それぞれに応じた深い知識や技術が必要になります。困っている部位があれば全身どこであれ対応できるような医師になりたいため、その目標に必要な知識やスキルを追求してきました。
今後様々なカテーテル治療を行う上で、個人にもそして施設としても土台として必要になってくる「CVIT認定医」の取得から始まり、大動脈瘤治療を習得するための腹部大動脈ステントグラフト実施医、下肢治療をする上で必要な浅大腿動脈ステントグラフト実施医、また、全身の血管疾患の知識が必要と思われ取得した脈管専門医など動脈硬化疾患やカテーテル治療に関連する資格を取得してきました。また、スキルだけではなく、疾患のさらに深い基礎的な問題や研究を学ぶため第2内科の大学院の門を叩き「博士号」の取得も行いました。修練を積み重ねることは自身のスキルアップ、キャリアを構築する上で重要ですし、従事する施設が専門手技の施設認定を獲得することにも繋がります。私たちの医局では、一人一人の要望・ニーズに応じて入局後から専門資格取得を考慮したプログラムを考えてくれます。

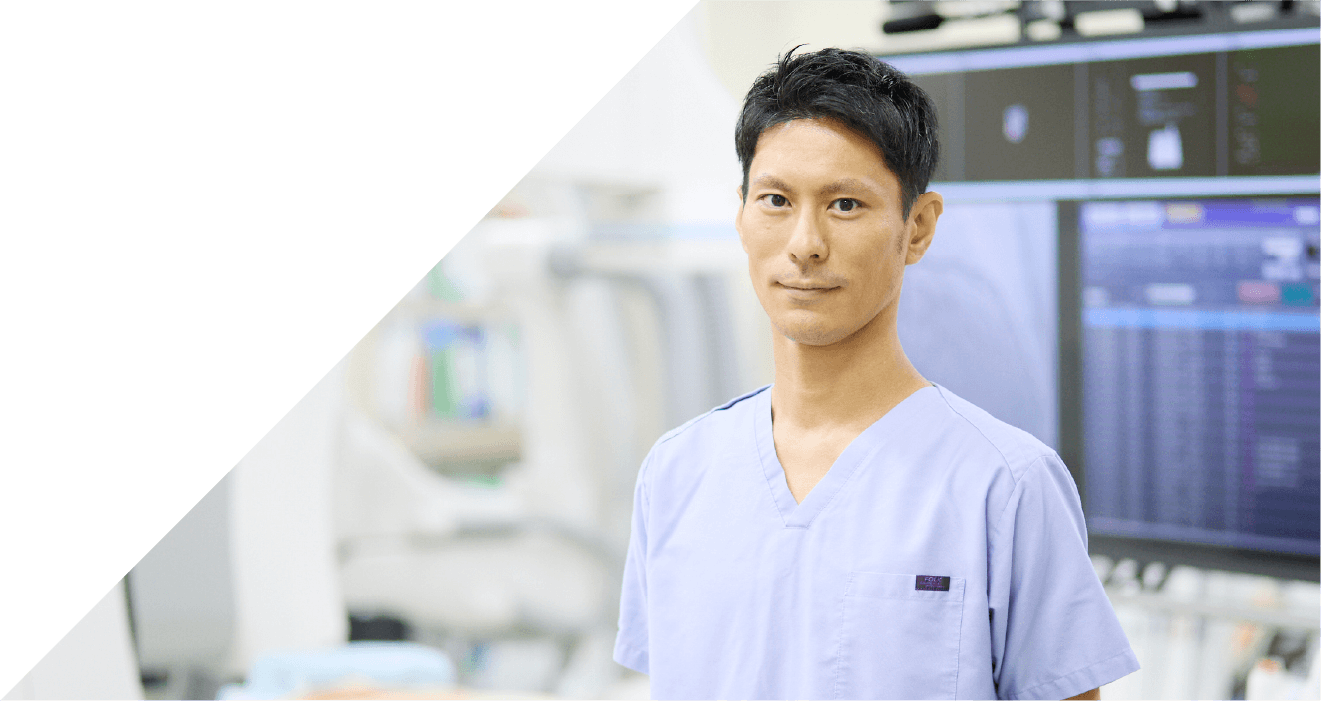
2014年入局
助教
仲 悠太郎
日々進歩が著しい循環器領域において、当院で未導入の治療を経験するために、国内ですでに治療を導入している病院での修練をしたいと考えました。海外留学とは異なり、言語の壁がないため手技の習得・理解には非常に有効な手段と考えて選択しました。
杏林大学を選んだ理由は?肺高血圧症と構造的心疾患(SHD)を学べる病院を探していました。その中で2020年に片岡教授が就任され、片岡先生が以前勤務された経験のある杏林大学をご紹介頂きました。
国内留学してみてどうだったか?自分の経験したことのない新たな環境での仕事は非常に刺激になりました。同じ治療方法でも新たな角度からの視点を得ることが出来たため、産業医大に戻ってきて治療方法の選択肢を多く持つことが出来ました。今後当院で開始予定のMitra ClipやTAVIなどの新規治療を事前に修練して持ち帰ることができたのも貴重経験となりました。
低侵襲治療としてMitra ClipやTAVIを当院に導入し、患者様にとってより多くの選択肢を提示できる医療を目標としています。選択肢が多いことは患者様のメリットがあると考えています。
入局希望者に向けて自分の希望に応じて国内留学先を紹介して頂き、「やりたいこと」に対して非常に理解がある医局だと思います。やる気を持って自分の「やりたいこと」を探すには非常に良い選択肢だと思いますの。一緒に患者様のための医療を提供できる仲間を随時募集中です。


専修医 中原 美友紀
私は元々北九州生まれ、北九州育ちです。私は医師3年目の6月に出産したため、循環器専攻医としての研修と育児が同時にスタートしました。育児と後期研修を両立させることがまず喫緊の課題であったこと、そして元々生まれ育った八幡地区で循環器内科医として研鑽を積みたいという思いもあり、2022年度までは出身大学の専攻プログラムで研修し、2023年度より産業医科大学内科専攻医プログラムに変更し、循環器専攻医として第2内科に所属する形となりました。
仕事のやりがいを感じるときは?日々の診療において治療が著効し患者が回復していく姿を見た時にやはり医師としてのやりがいを感じます。循環器内科医としては、特に心不全患者について他職種と連携し、退院後の生活まで配慮した方針を立てることに重きを置いています。また、第2内科のスタッフの先生方はそれぞれの専門分野で最新の知見を以て熱心に指導してくださるため、discussionや働いているその姿から学ぶことが非常に多く、日々全般の仕事に対するやりがいを感じています。
職場の環境はいかがですか?前述の通り、私は育児と循環器専門研修が同時にスタートした形だったため、常勤として働くことや専門医を取得することについてハードルが高いと感じていました。しかし、第2内科の先生方は非常に温かく迎えてくださり、スタッフの先生方は教育熱心で、限られた時間であってもきっちりと指導をしてくださいます。また、第2内科では病棟管理をチーム制で行っています。スタッフ1名、大学院生1名、専修医/修練医1名で少なくとも3人のチーム体制で担当患者について日々診療・discussionを行っています。大学病院では日中の外勤のために病棟医が不在となることも多いため、当科では常に縦チームと横チームで担当患者の診療状況について共有・引き継ぎを行っています。急な欠勤や学会・年休による不在の時でも常に大枠のチームもしくは小枠のチームの誰かが診療を継続する仕組みが整っているため、私のように育児と仕事の両立が1つの課題となっている医師にとっても大変有難い制度だと思います。また、時間外は必ず当科当直がいるため、ON/OFFがはっきりしており、病棟医が働きやすい仕組みが整っています。
今後の目標を教えてください。私は現在心エコーグループと肺高血圧症グループの一員として日々研修していますが、「前日よりも成長する」を積み重ねていき、臨床診療では患者に還元し、臨床研究では形に残すことが目標です。育児と仕事を両立するためには両方を100%にすることは不可能であり、成長のスピードもその分ゆっくりかもしれません。しかし細くとも長く循環器専攻医としての研鑽を続けていきたいと考えています。
大学病院では臨床・研究・教育が常に並行しており、各専門分野の講義やカンファレンス、研究についてのdiscussionなど希望すればいつでも参加できる環境であるため、充実した専門研修を送ることができます。また、女性医師としては妊娠中にカテーテル検査・治療に携わることができない期間がありますが、第2内科では心エコー専門研修や肺高血圧症分野の研究など、カテーテルが握れなくとも多様な働き方が可能です。現在もしくは将来的に育児と仕事の両立が不安、でも循環器や腎臓に興味があるという方はぜひ一度見学に来てください。

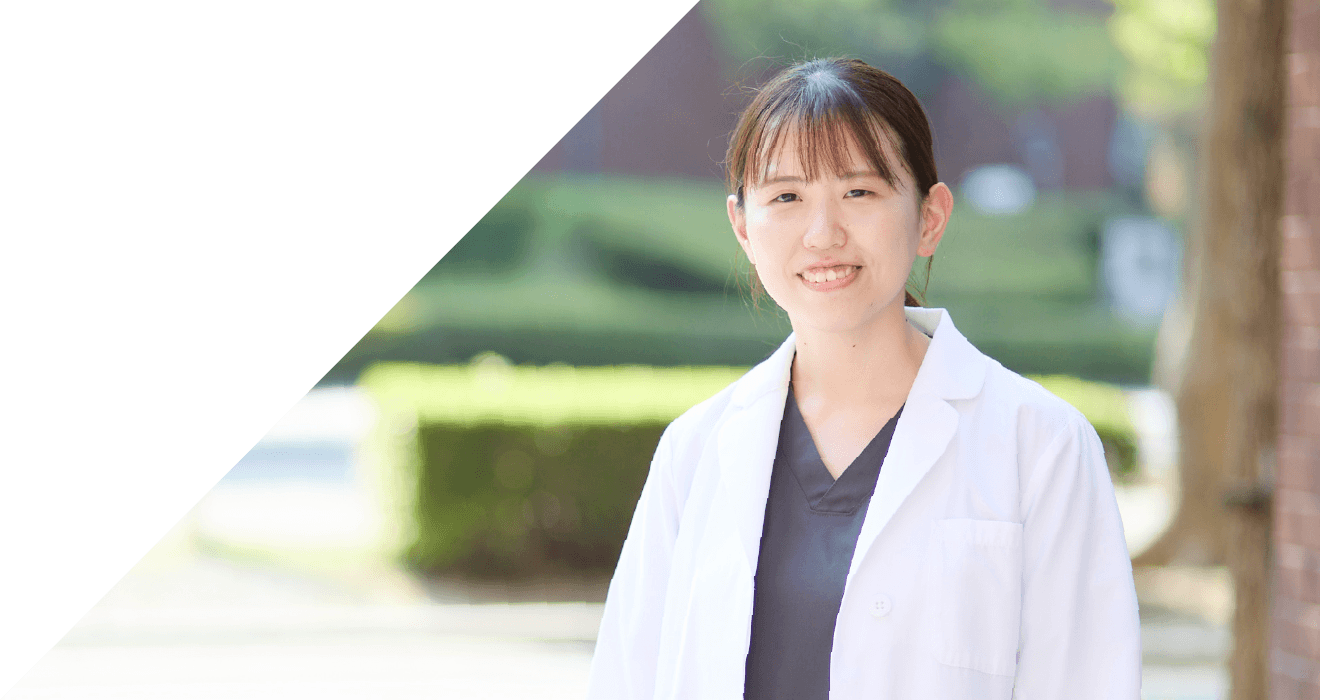
2024年入局
修練医
浦上 佑香
学生時代、研修医を経て、自分の専門をどこに置こうかと悩んだ時、患者さんと一緒に治療しながら長い付き合いができる科に進みたいと思ったことがきっかけです。内科領域の中でも循環器内科、腎臓内科疾患は生活習慣改善と内科治療の両方が必要と感じています。治療後もそれきりになることはなく、むしろそこから患者さんは病気と治療と長く向き合う必要があり、その時間を医師として支えられたらと思い、当科に興味を持ちました。医師だけでなく、看護師さんや薬剤師さん、リハビリの先生が関わって患者さんを支えているところや、患者さんの家族や患者さん自身の頑張りが予後に大きく影響するところに内科としてのやりがいを感じました。研修医時代に循環器内科、腎臓内科の先生方が患者さんから強く信頼されている様子をみて、憧れたことから2内科に入局しようと思いました。
仕事のやりがいを感じるときは?修練医になってから、研修医の時よりも悩んだり落ち込んだりすることがはるかに増えました。しかし先輩方のお力を借りながらも患者さんを治療し、患者さんの苦しそうな顔が楽そうな顔に変わったことを感じられた時、また患者さん本人から「楽になりました」と声をかけていただく時には研修医の時の何倍も喜びとやりがいを感じるようになりました。
チーム制で患者さんを見ているので、悩んだ時に相談しやすいです。
今後の目標を教えてください。自分の専門の科において人でできることを増やすこと、知識の引き出しを増やすことが目標です。
入局希望者に向けて一緒に仕事ができることを楽しみにしています。
