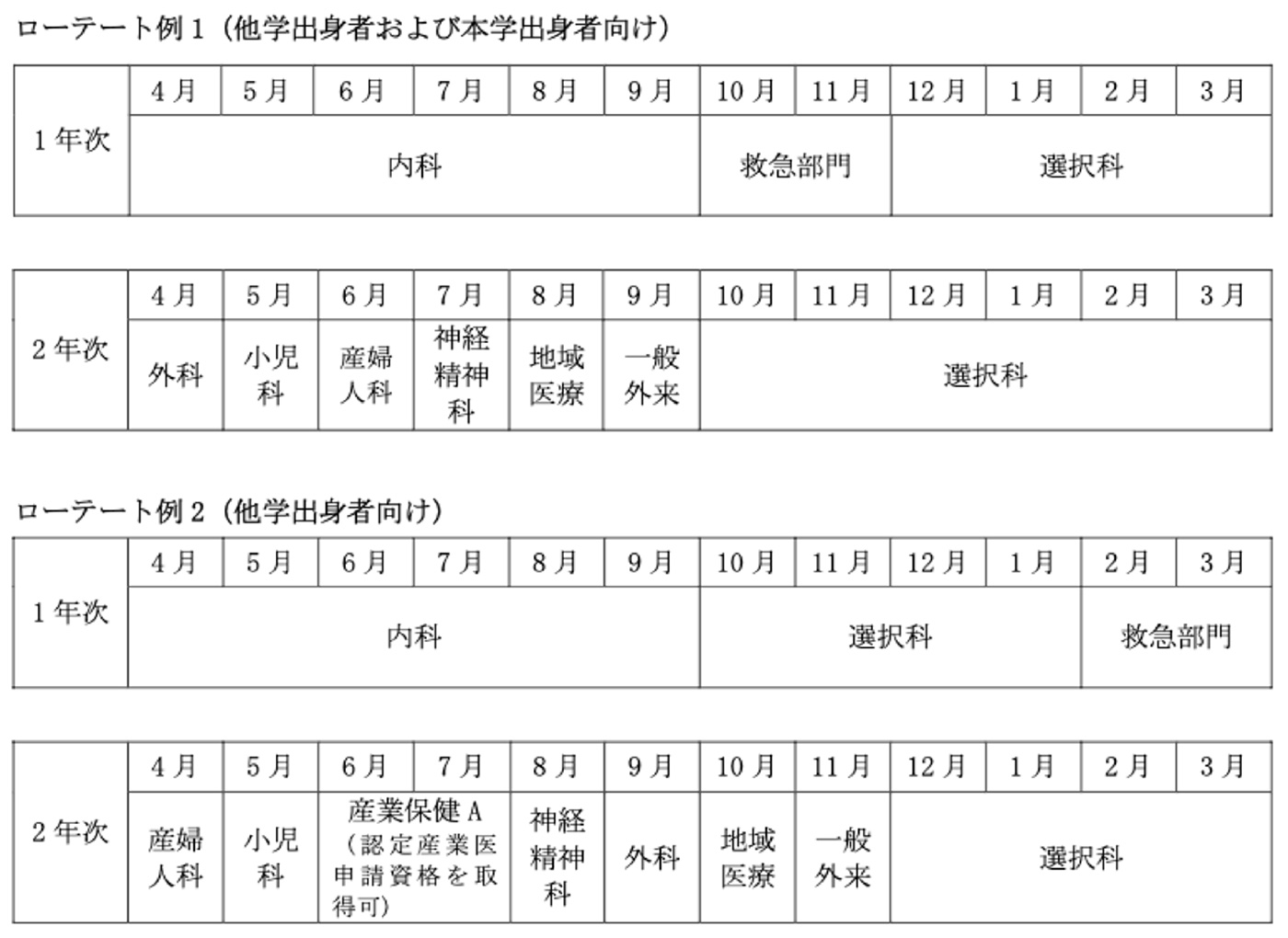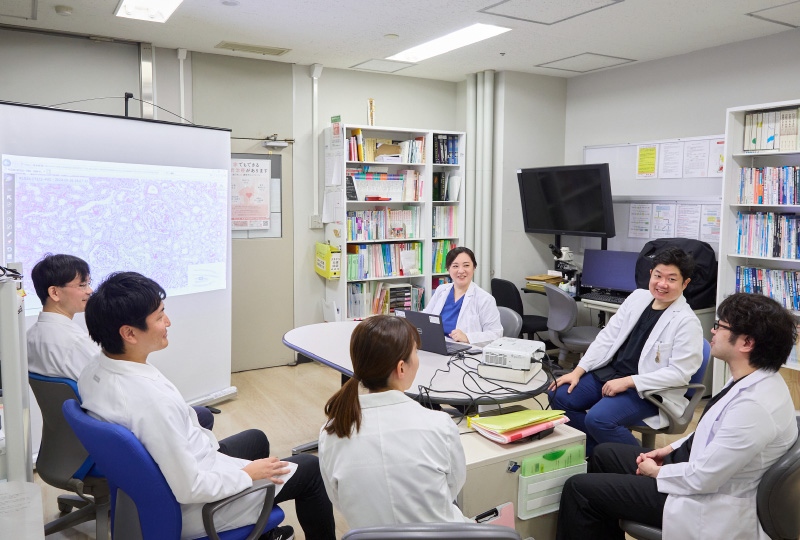当科では専門医取得を志す後期臨床研修医を募集しています。大学病院の特色上、複雑な背景を持つ患者さんが比較的多く来院されますが、専門的な手技や遺伝子レベルでの検査などを通じて、患者さん一人一人をより深く考察し、個人へフィードバックできるような体制を整えています。また、個人で問題を抱えることがないよう、常に周りと情報共有を行い、チームで診療にあたる体制をとっています。その他、基本的な手技や知識を勉強できる時間を確保したり、心電図などの判読を得意不得意に関わらず一定以上のレベルに到達させるための育成システムも構築しています。それらを通じて、新内科専門医制度の内科専門医・総合内科専門医をはじめとした以下の数多くの専門医取得を目指します。
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会専門医
- 日本脈管学会脈管専門医
- 日本不整脈心電学会不整脈専門医
- 日本超音波医学会超音波専門医
- 日本腎臓学会腎臓専門医
- 日本透析医学会透析専門医
- 日本アフェレシス学会認定専門医 など他多数
また、当講座では臨床だけでなく、研究にも重きを置いています。日常診療で浮かんだ疑問に対して答えを導き出すため、基礎研究から臨床研究まで広く行える研究環境を整えています。
循環器内科
片岡診療科長と11人のスタッフによる外来診療に加え、診療助教、専門修練医、臨床研修医、大学院生を含めたチーム編成での病棟業務を通じて、開業医の先生、市中病院の先生から数多くの患者さんを紹介いただき、24時間365日特定機能病院としての役割を果たしています。高度な専門医療が要求されるため、当科では主に3つの分野に分けて説明します。
カテーテル治療:最新技術で精密な診断と治療を
カテーテルによる虚血性心疾患の診断と治療は、循環器内科の醍醐味の一つです。当科では、冠動脈造影はもちろん、負荷心エコー、冠動脈CT、心筋シンチグラフィなど、多彩な検査法を駆使して精密な診断を行います。特に注目すべきは、最新の血管内エコーと光干渉断層撮影装置を用いた冠動脈プラークの詳細評価です。これにより、患者さん一人一人の病態に最適な治療方針を立てることができます。
治療面では、最新の薬剤溶出性ステントや薬剤コーティッドバルーンを用いた先進的な治療を行っています。さらに、プレッシャーワイヤーを使用して心筋虚血を評価し、インターベンション治療の適応や標的部位を決定する高度な技術も学べます。高度石灰化病変に対しては、ロータブレーターやダイヤモンドバックなどのアテローム切除型血管形成術も積極的に導入しており、複雑症例への対応力も養えます。
虚血性心疾患だけでなく、肺高血圧の早期発見を目指した検査や血栓が原因で生じる肺高血圧症に対するカテーテル治療も積極的に行っており、県外からの紹介も受け入れています。また、肺高血圧はその原因検索を行う上で、膠原病や呼吸器内科および放射線科とカンファレンスを通じて連携を取り合い、包括的に診療できる体制を整えています。
心エコー:運動負荷心エコー図検査で隠れている病態をあぶり出す
心エコー図検査は循環器診療の診断・治療方針決定の要となる技術で、当院では年間8000件以上の心エコー図検査を行っている心エコー図専門医研修施設です。最新の装置を用いて経胸壁心エコーだけでなく、薬物・運動負荷心エコー、経食道心エコー、3次元心エコー図検査まで行っており、本分野の知識を一通り経験しながら学ぶことができます。特にエルゴメーターを用いた運動負荷心エコー図検査は年間100件以上と九州でも最大の件数を誇る施設の一つとなっており、安静時では分からないような異常所見の早期発見につながっています。また、検査レポートを完成させて終わるだけでなく、気になった症例は後日全員でフィードバックを行い、知識や経験の共有を行い専門的なスキルを高めています。
不整脈治療:最新デバイスと高度な技術を駆使して
不整脈診療は、テクノロジーの進歩とともに急速に発展している分野です。当科では、カテーテルアブレーション、植込型除細動器(ICD)、ペースメーカの植え込みなど、幅広い治療法を学ぶことができます。特に注目すべきは、心不全患者の心機能改善に優れた効果を発揮する心臓再同期療法(CRT-D)です。また、失神の原因診断にはチルトテーブルを用いたhead-up tilt検査や植込み型ループ式心電計(ILR)を活用しており、難しい症例の診断スキルも磨くことができます。さらに、ペースメーカの電池交換やILRの設置を日帰り外来手術で行うなど、患者さんの負担軽減にも配慮した先進的な取り組みを学べます。また、デバイスを入れた患者さんが社会復帰できるよう、両立支援課とも頻繁に情報の共有を行い、病院の中だけではなくより患者さんの日常に寄り添う診療を目指しています。
以上、それぞれの専門分野の話をしましたが、実際に当院で行われている治療成績と特殊治療についてまとめます。
2023年度実績
| 検査・治療項目 |
件数 |
| 心臓カテーテル検査 |
424 |
| 冠動脈インターベンション |
112 |
| EVT |
71 |
| 経胸壁心エコー |
8364 |
| 経食道心エコー |
259 |
| 運動負荷心エコー |
112 |
| ペースメーカ植え込み |
66 |
| ICD/CRT-D |
14 |
| 植え込み型心電計 |
19 |
| アブレーション |
129 |
- 特殊治療
- 閉塞性肥大型心筋症(HOCM)に対する経皮的中隔心筋焼灼術(PTSMA)
- 腎動脈や下肢動脈の狭窄・閉塞に対するカテーテルインターベンション
- 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術(2022年度から開始)
- 慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術
- 卵円孔開存閉鎖術(2022年度から開始)
- 左心耳閉鎖術(2022年度から開始)
2022年度より新たに当院で実施可能となった手技が増えていますが、今後はさらに増えていく見込みで、それに向けて全員が一丸となり取り組んでいる最中です。
腎臓内科
腎臓内科グループは宮本診療副科長を含む4名のスタッフに加え、診療助教(大学院生含む)、後期修練医、臨床研修医により診療を行っています。現時点で腎臓内科指導医は3名、診療助教2~3名、後期修練医1-2明、研修医1~2名で、全員が協力、分担し診療を行っております。当院は日本腎臓学会・日本透析医学会の認定教育施設であり、当院で研修を行うことで腎臓専門医、透析専門医の取得が可能となります。当院腎臓内科では下記疾患・治療に対して循環器グループとも協力し診療を行っています。
- ①慢性腎臓病(CKD)、急性腎障害(AKI)、急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の診断・治療
- ②血液透析:新規血液透析導入、バスキュラーアクセス手術、シャントPTA などの透析アクセストラブルに対する対応、合併症の治療、他科入院透析患者のバックアップや周術期管理、免疫吸着法(SLE、重症筋無力症、尋常性乾癬)、白血球除去療法(関節リウマチ、潰瘍性大腸炎)、血漿交換療法
- ③腹膜透析:新規腹膜透析導入、合併症の治療
また、中央診療部に位置する腎センターでは上述の血液浄化療法に加え、外来腹膜透析も行っています。重症症例や救急症例の急性血液浄化療法や、新生児・小児の血液浄化療法にも随時対応をしています。日本腎臓学会研修施設や日本透析医学会認定施設として、専門医研修も行われています。腎センターで開発した電子カルテ用血液浄化療法監視システムを運用し、看護師や臨床工学技士の協力電子カルテ用血液浄化療法監視システムを運用し、看護師や臨床工学技士の協力も得て、事故のないよう細心の注意を払い日々の業務を行なっています。また、後期修練医中においては関連施設での腎臓内科としての修練も可能です。関連施設としては北九州総合病院、済生会八幡総合病院、門司労災病院、小波瀬病院等があり、今後更なる関連施設の増加を見込んでいます。関連施設と密な連携をとることでより幅広い腎臓内科領域の診療にあたることが可能な体制となっております。
以上が当科の特色になります。一般的な診療から高度な専門知識が問われる内容まで幅広く扱っていますので、ぜひ気軽にご相談いただければ幸いです。
基礎研究
基礎研究班では、古賀純一郎講師と大学院生を中心に心血管病が起こるメカニズムの解明とそれに基づいた新しい治療の創出を目標に研究を行っています(基礎研究ページへ)。古典的な病理学的解析に加え、単一細胞イメージングによる時空間解析、マルチオミクス解析など最先端技術を用いた研究を行っています。 基本から最先端の技術を扱える研究環境で、自立した研究者 になれることを目標に、マウスの扱い方からそれぞれの高度な解析まで自身で完結できるよう丁寧に指導を行っています。
日常診療で生じた疑問に対して自身で立ち向かえる力を持つことは長い医師人生を有意義なものしてくれると思います。興味のある方は、気軽に相談、見学にお越し下さい。